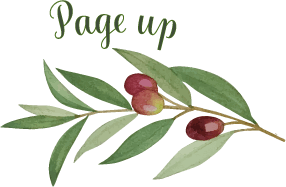活動情報
-

- クリスマスについて考えてみよう!
- <p>1. クリスマスの文化的な違い:<br>– アメリカでは:<br>– 1年分の生活必需品(下着や衣類など)が主なプレゼント<br>– 家族で感謝を分かち合う宗教的な行事<br>– 子どもの「欲しいもの」をもらえる日という概念は一般的ではない</p><p>– 日本では:<br>– 子どもが欲しいものを選ぶ習慣がある<br>– より商業的な側面が強い<br>– 家庭によって祝い方が大きく異なる</p><p>2. 大切な考察点:<br>– クリスマスの本来の意味を考え直す必要性<br>– 誕生日と区別することの重要性<br>– 日常的に物を買い与えられている子どもたちの感謝の気持ちを育む機会に<br>– 家庭ごとの違い(サンタの存在、祝い方など)への配慮</p><p>3. 教育的な観点:<br>– 感謝の心を育むきっかけとしてのクリスマス<br>– 子供たちの間での格差への大人の対応の重要性<br>– 物をもらうことが当たり前になることへの懸念</p><p style="color:#009966"><strong>クリスマスを通じて、文化の違いや子育ての価値観、感謝の心の育み方について考えてみてはいかがでしょうか♪</strong></p><p style="color:#009966"><br></p><p style="color:#000000"><a href="https://mamilia.koelab.work/071-2/">クリスマスについてかんがえてみよう!</a></p>
-

- 12月の過ごし方‐ハレとケ‐
- <p>1. 12月の特徴と課題<br> – 年末が近づき、クリスマスやお正月などのイベントが多い時期<br> – 現代は「ハレ」の日(特別な日)が多く、刺激の多い生活になっている<br> – 大人は準備で忙しくなりがちだが、子どもはその状況を理解できていない</p><p>2. 子どもへの影響<br> – 親の忙しさや普段と違う様子を敏感に感じ取る<br> – 反応として、親から離れる、だだをこねるなど様々な行動が現れる<br> – 結果として親子ともにストレスフルな状況になりやすい</p><p>3. 提案される対策<br> – 12月上旬は「ケ」(日常)の時間として意識的にゆっくり過ごす<br> – 年賀状作りや大掃除を子どもと一緒に行う<br> – 特別なイベントばかりではなく、近所の公園への散歩など、シンプルな活動を取り入れる</p><p>4. メリット<br> – 子どもとの日常的なコミュニケーションが深まる<br> – 年末年始の特別な時期をより印象深く楽しめる<br> – 親子ともに心の余裕を持って過ごせる</p><br><ul><li style="color:#009966">12月の忙しい時期こそ、意識的に日常を大切にし、「ケ」の時間を作ることで、後半の「ハレ」の時期をより充実して過ごせますよ♪</li></ul><br> <div><a href="https://mamilia.koelab.work/070-2/">12月の過ごし方‐ハレとケ‐</a></div>
-

- 「カウンセリング」は何のためにするの?
- <div><span style="color:#3300ff"><span style="color:#000000">みなさんは</span><strong>心理カウンセリング</strong></span>と聞いてどんなイメージを思い浮かべますか?<br></div><div><br></div><div>心が弱い人が受けるもの?</div><div>心が病んだ人が受けるもの?</div><div><br></div><div>一般的にはそんなイメージがあるかもしれません</div><div><br></div><div>日本ではカウンセリングが受けられる場所が病院やクリニックくらいだったという過去の影響かもしれませんが、</div><div>最近ではいろんなところで「カウンセリング」という言葉を見聞きするようになりました。</div><div>美容室やエステでも”カウンセリング”をしてから施術ですよね。</div><div><br></div><div>簡単に言うと<span style="color:#0000ff">「あなたの現状を聞かせてください」</span>という感じでしょうか?</div><div><br></div><h4><strong style="color:#3300ff">何に困っていて、どうなりたいと思っているのか</strong></h4><div><br></div><div>本人のニーズや希望を聞いてから「では、カットしていきますね~」ですよね😁</div><div><br></div><div>心理カウンセリングも同じで</div><div><br></div><h3 style="color:#ff3399">今何に困っていて、それがどうなったらいいと思っているのか?</h3><div><br></div><div>を回数重ねて聞いていきます。</div><div>一人でもできるよ~と思う方もいるかもしれません。<br></div><div><br></div><div>頭の中で整理整頓が上手にできる方は<div>それはそれでOKです。</div> <div><br></div><div>でも、</div><div>自分の体調が悪いとき、</div><div>経済的な不安があるとき、</div>何もかもがうまくいかないとき など</div><div><br></div><div>そんなときにずっと一人で考え続けていると</div><div>なかなか解決策が得られなかったり、</div><div>思わしくない選択をしたり…</div><div><br></div><div>とより苦しい状況に<span style="color:#3366cc">自分で</span>追い込んでしまうことも少なくないです。</div><div><br></div><div style="color:#ff0099"><strong>【カウンセリングの効果】</strong></div><div><ul><li>誰かに話をすることで、感情が解放されます</li><li>頭の中で考えていたことが整理されます<br></li><li>自分の本心に気づきやすくなります</li><li>自分にない考えや気づきをえられます</li></ul></div><div>このようなことから、<span style="color:#3300ff">生きやすくなる</span>のではないでしょうか。</div><div><br></div><div>悩んでいることが「子どものこと」となると</div><div>一人で考えて答えをだすことは、とても責任重大で、もしかしたら間違った選択になることもあります。</div><div><br></div><div>そして、我が子といえども自分ではない別人です。</div><div>我が子のことを自分事とは切り離して考える必要があるときもあります。</div><div><br></div><div>それを一人でやるのは難しい!</div><div><br></div><div>自分を知るため、現状を整理するため、より生きやすくなるため…</div><div><br></div><div>“あなたの理由”を大事に、カウンセリングを利用してみませんか😊</div><div></div>
-
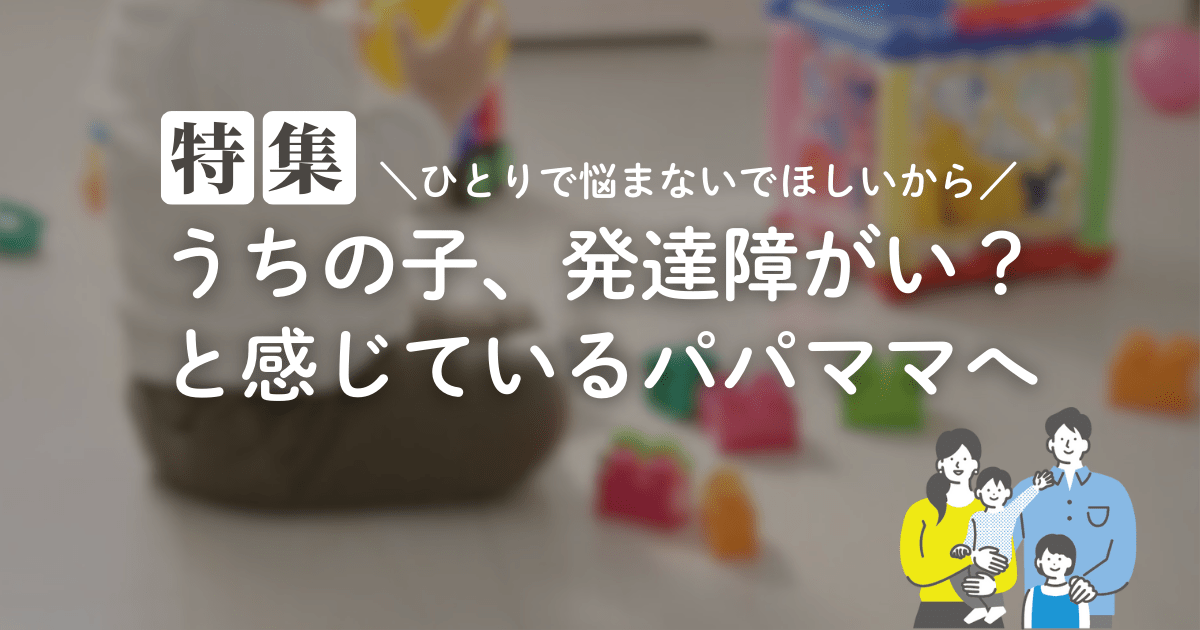
- リトルママにインタビューが掲載!
- 最近よく耳にする<span style="color:#0033ff">「発達障害」</span>について<div><br></div><div>みなさんはどれくらい知っていますか?</div><div>説明するのは難しいけど…</div><div>一度は「我が子もそうなのかな?」と思ったことがあるのではないでしょうか</div><div><br></div><div>発達障害があってもなくても、こどもにとって親はとっても大切な存在です。</div><div>子育てをしていると、不安になるのはよくわかります</div><div>しかし、不安に圧倒されて、目の前の我が子が見えなくなっていてはもったいない…</div><div><br></div><div>もしかして…と思ったときにどうしたらいいのかを、インタビューに答える形でまとめてもらっています!</div><div><br></div><div>ぜひ読んでみてください♪→<a href="https://media.l-ma.co.jp/kosodate/325026/">リトルママ</a></div>
-
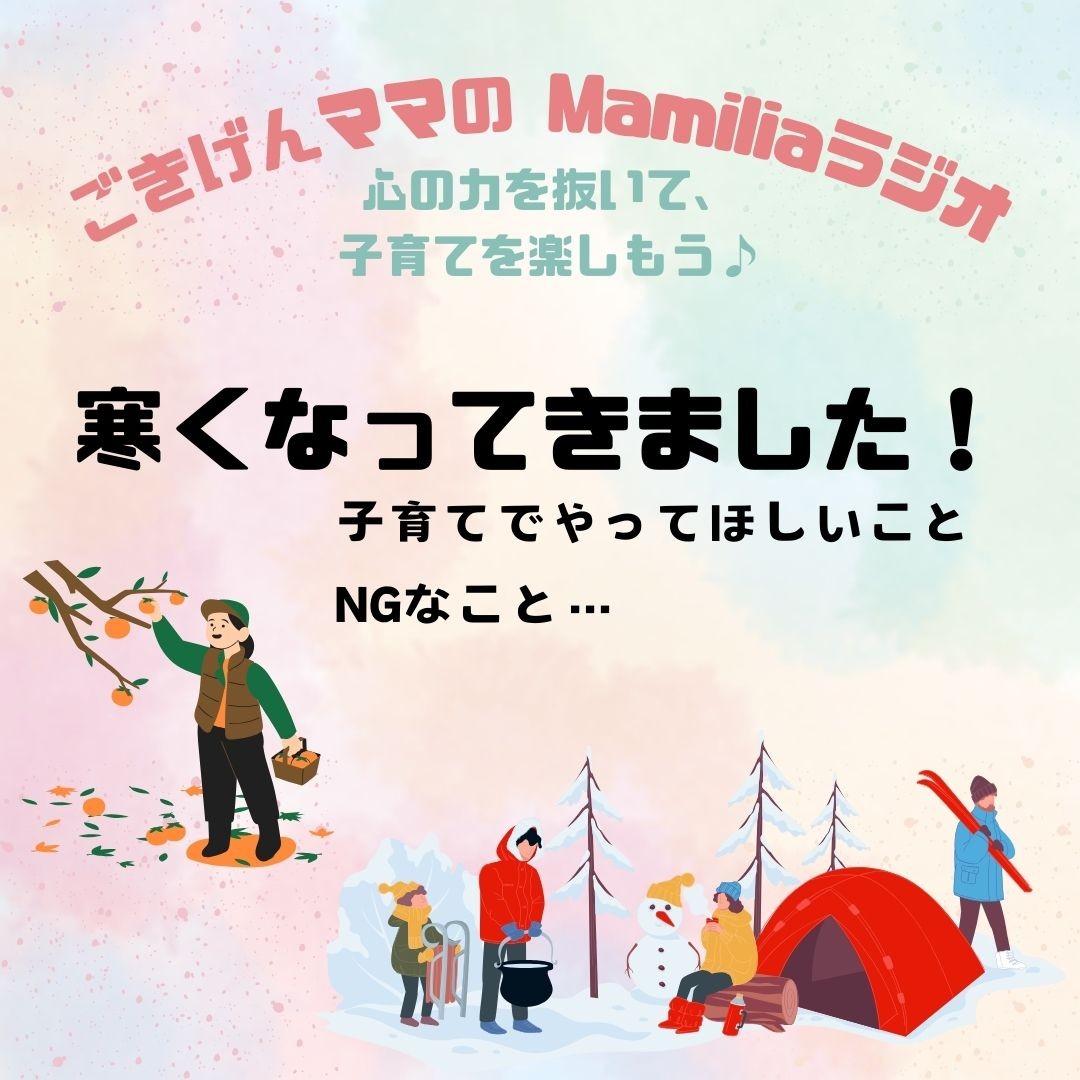
- 寒くなってきました!子育てでやってほしいこと、NGなこと…
- <p>暖かい日が続いてましたが、急に寒くなってきましたね🥶</p><p>寒暖差アレルギーという言葉も、日常生活でよく聞くようになりましたね💦</p><p>子どもたちの鼻水がでるようになってくると…咳が出始めると…</p><p>ちょっとした体調変化を感じ取って、すぐに対応をしたくなると思いますが、やりすぎ注意!を意識できたらいいですね。</p><p>病気にかかりにくい体を作ることも、日常生活の過ごし方の影響を受けます。</p><p>そして、</p><p>実は、</p><p><span style="color:#ff6666"><strong>子どもたちは寒い季節が好きなんですよ!</strong></span><br></p><p>体を強くするために&寒い時期を楽しく過ごす方法をお伝えします😊</p><p>★ 冬の子育てで大切にしたいこと</p><p><span style="text-decoration:underline">1. 自然体験</span><br> – 外に出て散歩する<br> – 落ち葉やどんぐりを拾う<br> – 季節の変化を一緒に観察する<br> – 葉っぱの形や色の違いを楽しむ</p><p><span style="text-decoration:underline">2. 五感を使った学び</span><br> – 落ち葉を踏む音を聞く<br> – 冬の匂いや風を感じる<br> – 自然の変化を体全体で体験する</p><p><span style="text-decoration:underline">3. 子どもの好奇心を育む</span><br> – 「なぜ?」の質問に付き合う<br> – 子どもの発見を一緒に喜ぶ<br> – 自然への興味を大切にする</p><p><span style="text-decoration:underline">4. 体を動かす</span><br> – 寒さを理由に家に閉じこもらない<br> – 外で走ったり遊んだりする<br> – 体を動かすことを楽しむ</p><p>目的は、</p><p><span style="color:#0033ff"><strong>子どもの好奇心と学ぶ力を大切にし、自然とのつながりを感じる</strong></span>こと。<br> 寒くなる時期は季節の変化を感じやすいタイミング!<br> 楽しみながら季節を感じましょう♪</p><p>★ 冬の子育てでNGなこと</p><p><span style="text-decoration:underline">1. 服装のこと</span><br> – 厚着しすぎない<br> – たくさん重ね着させない<br> – 汗をかいたらすぐ脱がせる</p><p><span style="text-decoration:underline">2. 子どもの活動を制限しないで!</span><br> – 寒いからといって外に出ない<br> – 公園で動かずにじっとしない<br> – 寒さを理由に遊びを止めない</p><p><span style="text-decoration:underline">3. 子どもの自然な探求心を抑えないで!</span><br> – 落ち葉やどんぐりを拾うのを楽しもう<br> – 季節の変化に興味を持つことを楽しもう<br> – 子どもの好奇心を会話を通して広げよう</p><p>ポイントは、</p><p><strong>寒さを理由に子どもの活動と学びを制限しない</strong>こと。</p><p>子どもの自然な好奇心と体の機能を信じることが大切です。</p><p><br></p><p><a href="https://mamilia.koelab.work/069-2/"><strong>寒くなってきました!子育てでやってほしいこと、NGなこと…</strong></a></p>
-
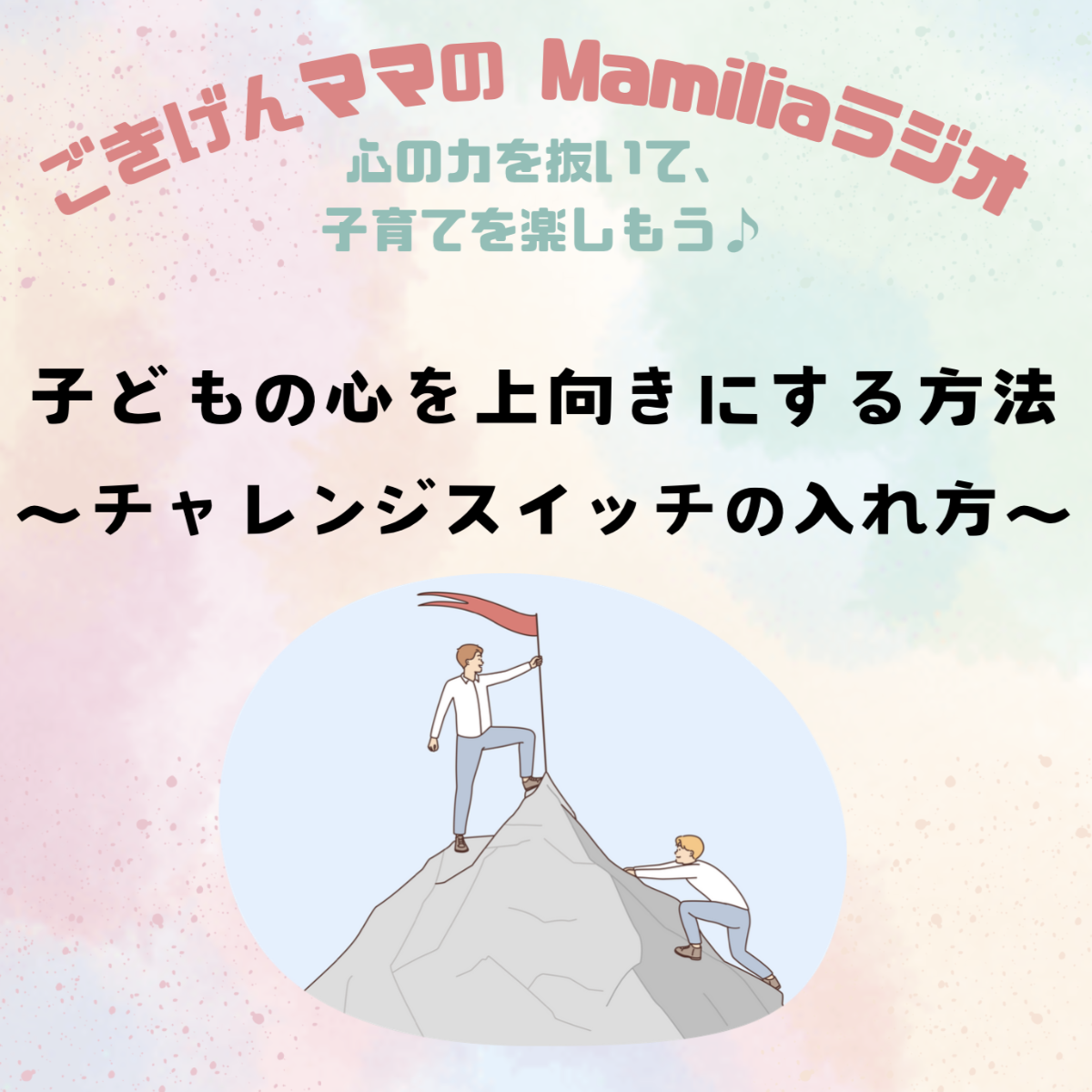
- 子どもの心を上向きにする方法~チャレンジスイッチの入れ方~
- <p>子どもは<strong>本来</strong>とても<span style="color:#ff3399"><strong>チャレンジ精神に満ちた生き物</strong></span>です。</p><p>赤ちゃんの時期から、寝返りやはいはい、気になるものを触るなど、様々なことにチャレンジしていきます。</p><p>しかし、成長とともに、叱られる経験が増えるなど、徐々にチャレンジ精神がしぼんでいく傾向にあります。(これはこれで大事なことではありますが…)</p><p>そうしたお子さんの挑戦心を呼び起こすためのポイントを紹介します!</p><p><span style="text-decoration:underline">1. 大人自身が楽しむ姿を見せること</span><br> – 公園でターザンロープに挑戦して欲しいのにしてくれない時など、大人も楽しむ姿を見せると、子どもも挑戦したくなります。</p><p><span style="text-decoration:underline">2. 様子を見守る子どもへの丁寧な働きかけ</span><br> – じっと見守っているだけの子どもでも、実は頭の中で活発に考えていることが多い。その子の内面に寄り添い、会話を重ねることが大切です。</p><p><span style="text-decoration:underline">3. 子どもの気持ちをよく理解する</span><br> – 子どもの今の関心事や考えていることを把握し、それに合わせて働きかけることが重要です。</p><p><br></p><p>つまり、<span style="color:#0033ff">子どもの個性を理解</span>しながら、<span style="color:#0033ff">子供の探求心に寄り添い</span>、<strong style="color:#0033ff">大人も一緒に楽しむ</strong>、そういった関わり方が子どものチャレンジ精神を呼び覚ます上で大切だということですね。</p><p>皆さんの子育てに役立てていただければと思います♪</p><p><br></p><p><strong><a href="https://mamilia.koelab.work/068-2/">子どもの心を上向きにする方法~チャレンジスイッチの入れ方~</a></strong></p>
-

- 社会で子育て!“共同養育”について
- <p><span style="color:#0033ff"><strong>”共同養育”</strong></span>という言葉、聞いたことありますか?</p><p><br></p><p>今の社会は核家族が普通の家族形態になっているので、<br>現代社会では‘核家族で‘子どもを育てることがスタンダードです。</p><p>しかし…</p><p>その養育スタイルは、実は私たち人間にとって<span style="color:#009999">とっても不自然なこと</span>なんです…</p><p>昨今の子育ての大変さ、子育ての悩みの深刻化、多様性…いろんな問題が生じるのも当たり前と言えます。</p><p>私たちは不自然なことを一生懸命頑張って取り組んでいる…なんだか健気(けなげ)じゃないですか?</p><p><br> そんな自分を褒めつつ、子どもを育てる側にとって、そして育てられる側にとって自然な養育環境ってどんなものか…を紹介します♪</p><p><span style="text-decoration:underline">1. 共同養育の概念について</span>:<br> – もともと人類は村全体で子育てをする「共同養育」をしていた<br> – これは人間の遺伝子情報に組み込まれている自然な形態<br> – 原住民の研究から、複数の大人が子育てに関わることが自然な形だった</p><p><span style="text-decoration:underline">2. 現代の課題</span>:<br> – 現代社会では共同養育が難しくなっている<br> – 核家族での子育ては人間の遺伝子情報に反している<br> – これが育児ストレスや産後うつなどの原因の一つとなっている可能性</p><p><span style="text-decoration:underline">3. 解決への提案</span>:<br> – 社会との繋がりを持つことの重要性<br> – 支援制度の活用<br> – 子育て中の親が助けを求める力の必要性</p><p>夫婦で力を合わせるのも素敵ですが、<span style="color:#ff6666"><strong>いろんな人が関わった方が、子どもの育ちにメリットだらけです</strong></span>。</p><p>勇気を出して、社会とつながっていきましょう♪</p><p><br></p><p><strong><a href="https://mamilia.koelab.work/067-2/">社会で子育て!”共同養育”について</a></strong></p>
-
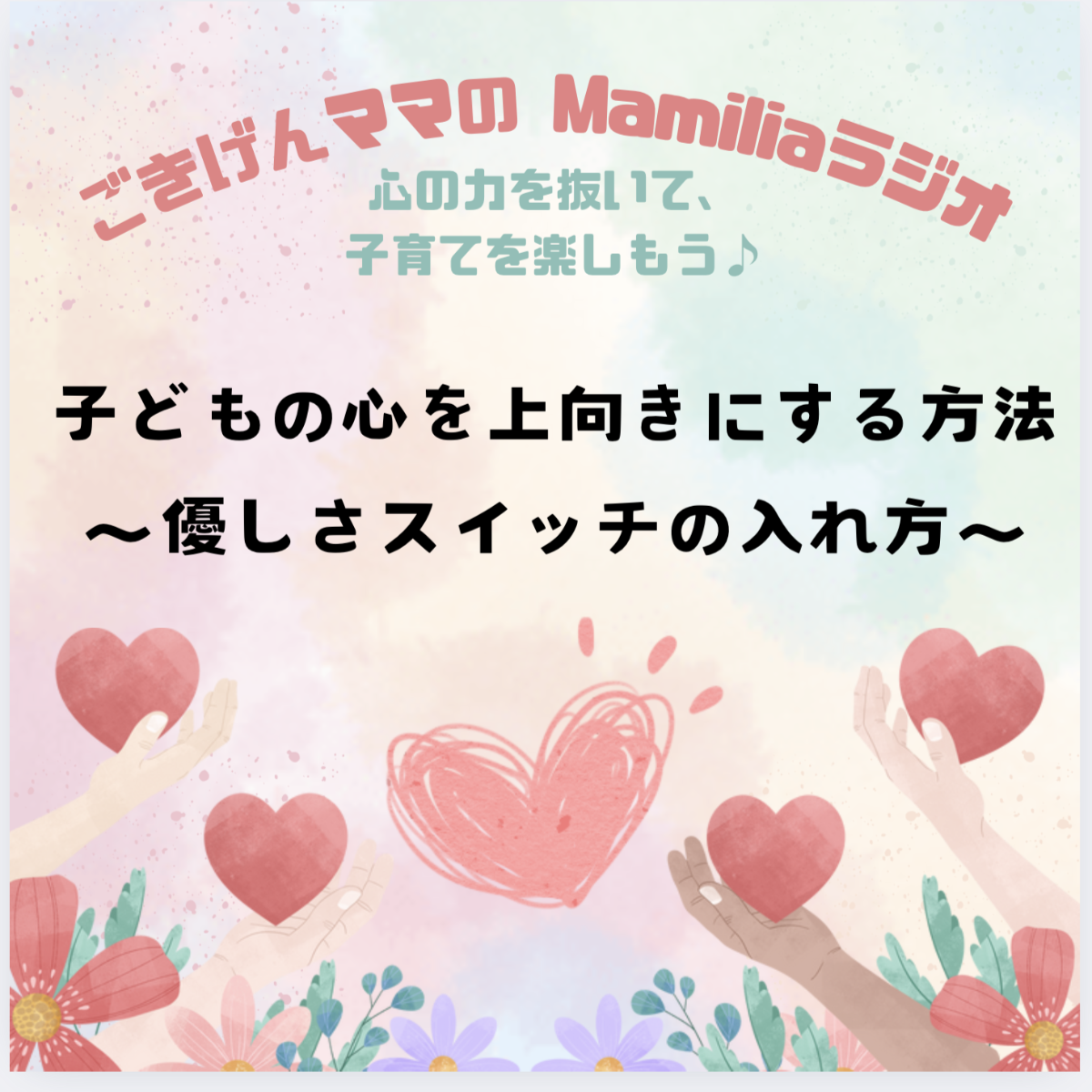
- 子どもの心を上向きにする方法~優しさスイッチの入れ方~
- <p><span style="color:#ff6666"><strong>我が子には、思いやりがあって優しい人であってほしい</strong></span>…と願う方は多いのではないでしょうか。<br> では、優しい人になってもらうために、</p><p>子育てでどのようなことをしていますか?</p><p>優しい行為をさせようと直線的な関わり方をすると、あまり効果は得られません…</p><p>今回は、我が子に優しい人になってもらえるよう、日頃の子育てでどのように関われば良いのかを話しています。</p><p><span style="text-decoration:underline">1. 親の過度な「正しい行動」への指導について</span>:<br> – 親は子どもに思いやりや優しさを教えたい気持ちから指導してしまう<br> – この方法は逆効果になる可能性がある<br> – 子どもは「自分より他人が大事」「自分の気持ちを分かってくれない」と感じてしまう</p><p><span style="text-decoration:underline">2. 子どもの思いやりの発達について</span>:<br> – 2-3歳での「思いやり」的な行動は、主に大人の真似や学習した行動<br> – 5歳以降になって初めて、本当の意味での思いやりが芽生える</p><p><span style="text-decoration:underline">3. 5歳以降の発達的特徴</span>:<br> – より深い人間理解が可能になる<br> – 自分の行動が他者に与える影響を理解できる<br> – 「痛みを伴った優しさ」を理解し始める<br> – 罪悪感や後悔の気持ちを理解できるようになる</p><p><span style="text-decoration:underline">4. 重要な学びのプロセス</span>:<br> – 他者を傷つけてしまう経験自体が重要な学びとなる<br> – この経験を通じて、心からの謝罪や反省が生まれる<br> – 将来の行動改善につながる深い理解が育まれる</p><p><span style="text-decoration:underline">5. 大人の効果的な関わり方</span>:<br> – 「こうすべき」という指導ではなく<br> – 「あなたはどうしたかったの?」と子どもの気持ちを聞く<br> – 「不本意ながらこうなっちゃったんだよね」と状況を理解する<br> – 「あなたの気持ちはわかってるよ」と共感を示す</p><p><span style="text-decoration:underline">6. アドボケイト(気持ちの代弁)の重要性</span>:<br> – 子どもの気持ちを言語化して代弁する<br> – 「今譲るべき」「ごめんねは?」といった指導的な声かけを避ける<br> – 「どうしても遊びたかったんだよね」と気持ちを認める<br> – 「じゃあどうしよっか」と一緒に解決策を考える</p><p><span style="text-decoration:underline">7. 5歳以降の関わり方</span>:<br> – 子どもは自然と「痛みを伴った優しさ」を理解するようになる<br> – 「ママ傷ついたわ」などと言って教える必要はない<br> – 子どもは周りの状況をよく観察し理解している<br> – 子どもが自発的に「ごめんね」と言ってきたら、そのまま受け止め「ありがとう」と返す</p><p>以上のように、子どもの感情発達を支援する上で、指導的なアプローチよりも、<strong style="color:#ff6666">感情に寄り添い、言語化を助けるアプローチが効果的</strong>です。特に<span style="color:#ff6666">5歳以降は、子どもの自然な感情の発達を信頼し、それを受け止めることが重要です♪</span></p><p><span style="color:#ff6666"><br></span></p><p style="color:#000000"><a href="https://mamilia.koelab.work/066-2/"><strong>子どもの心を上向きにする方法~優しさスイッチの入れ方~</strong></a></p>
-

- 発達障害ってなに?増えてるの?
- <h2>10月のマミポケのテーマは「発達障害」</h2><div>最近よく耳にするようになったワード「発達障害」について</div><div>どんなものか説明できますか?</div><div><br></div><div>わかるようで、よくわからない…という人は少なくないと思います。</div><div><br></div><div>実際、専門職といわれる人たちの間でも、その捉え方が微妙に異なり、</div><div>受診先が違えば、診断も変わる…ということもあります。</div><div><br></div><h3>子どもを育てる立場からすると、障害があるかどうかよりも</h3><h3><span style="color:#0033ff">「関わり方が知りたい」「なぜそういう言動をとるのか理由が知りたい」</span>のではないでしょうか?</h3><div><br></div><div>もちろん障害の有無が気になる場合もあるでしょうが、障害があってもなくても、関わり方を知りたいですよね?</div><div><br></div><div>マミポケでは、発達障害に見られる症状の背景をいろんな角度から探り、そりゃそうなるよね…と子ども理解を深めることから始めています。</div><div>それならこうしてみよう、これを変えてみよう…など</div><div><br></div><h3 style="color:#0033ff">背景が理解できると、対策が自然と浮かんできます。</h3><div><h4>専門家が対策を伝えても、家でできないことだと、実践できませんから</h4></div><h4><span style="text-decoration:underline">背景を理解したうえで、<span style="color:#ff0000">保護者自身が見つけた対策がもっとも子どもに届く方法</span>だとマミリアは感じています。</span></h4><div>自分で見つけた対策がうまくいくと自信も増しますよね💛</div><div><br></div><div>そんな自信を積み上げていく場所・仲間としてオンラインコミュニティ「マミポケ」はあります。</div><div><br></div><div>ぜひお気軽にご参加くださいね♪</div><div></div><div></div>
一歩踏み出して、子育てを楽にしませんか? ご相談・お問い合わせ

お電話|090-9481-0645 受付|10:00〜18:00/不定休